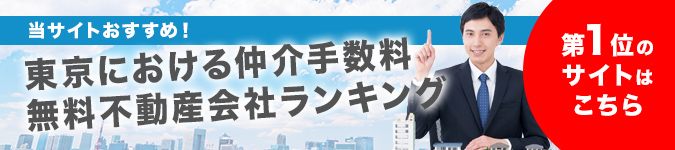不動産売買において利益相反取引に当たるのはどのような取引でしょうか。
また、利益相反取引に当たる場合はどのような手続きを踏めばいいのでしょうか。
この記事では「利益相反」の意味と会社法で規定された「利益相反取引」についてご説明した後、不動産売買における利益相反取引において必要な手続きを大きく4つのステップに分けて解説します。また、もし必要な手続きを踏まなかった場合の影響についてもお話します。
目次
利益相反とは
利益相反とは「ある人の一方の利益が、他方の不利益になること」を意味します。
たとえば、会社の取締役が自分の利益のために何らかの取引を行い、その取引によって会社が損害を被る時、取締役と会社の間に利益相反があります。
会社法による利益相反取引の規定
株式会社の取締役は「個人」としての立場を持つと同時に、取締役を務める「法人」としての利益を追求する立場にもあります。
取締役が個人として自らの利益のために何らかの取引を行う場合、その取引が法人(の株主)にとって不利益になるような取引を「利益相反取引」と言います。
会社法第356条は、取締役と株式会社の利益が相反する取引が行われる場合、当該取締役は取締役会または株主総会の承認を受けなければならないと定めています。
この定めは、取締役が個人の利益を追求することによって株式会社に損害が生じるのを防ぐことを目的としています。
なお、ここで言う「取締役」は代表取締役に限らず平の取締役も含みます。
利益相反取引には「直接取引」と「間接取引」がある
具体的にはどのような取引が利益相反取引に当たるのでしょうか。
利益相反取引は、取締役が直接取引に関わる「直接取引」と、取締役が直接取引に関わらない「間接取引」に分けられます。
直接取引
「直接取引」は会社法第356条2項に定められた取引で、取締役が自己の利益のために会社と行う取引を言います。
また、取締役が第三者の代理として行う取引も直接取引に含まれます。
たとえばA社の取締役がB社の取締役を兼任しており、当該取締役がB社の代理としてA社と取引を行う取引においてB社のみに有利な取引を行う可能性もあります。
【会社法第356条2項】
取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
直接取引の具体例:
- 取締役が法人から贈与を受ける
- 取締役と法人が金銭消費貸借契約を結ぶ
- 取締役の債務を法人が免除する取引
- 法人Aの取締役が法人Bの代理として法人Aと行う取引
間接取引
会社法第356条3項に定められた「間接取引」は、法人が取締役以外の者と行う取引の内、法人と取締役の利益が相反するものを言います。
【会社法第356条3項】
株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
間接取引の具体例:
- 取締役の第三者に対する債務を法人が保証する
- 法人が取締役の第三者に対する債務を引き受ける
- 取締役の第三者に対する債務を担保するため法人名義の不動産へ抵当権を設定する
不動産売買における利益相反とは?
では不動産売買における利益相反取引にはどのような取引があるのでしょうか。
具体例を挙げて解説します。
利益相反取引に当たる不動産売買の具体例
不動産売買において利益相反取引に当たるのは、法人と当該法人の取締役の間の取引です。
たとえばよくあるケースとして、法人Aの代表取締役Xが個人で所有する不動産を、節税目的で法人Aに不動産を売却する取引があります。
この場合、代表取締役Xが法人Aへの売却する際の価格が、時価より高くても低くても利益相反取引に当たります。
法人が取締役に不動産を売却する場合も利益相反取引に当たります。
また、法人Aと法人Bの取締役(または代表取締役)を同一人物Yが兼任しているといった場合、法人Aと法人B間の不動産売買も利益相反取引に当たります。
なお、取締役から会社へ不動産を贈与する場合など、明らかに会社の不利益にならない取引は利益相反取引に当たりません。
不動産売買が利益相反に当たる場合どうしたらいい?
では、不動産売買が利益相反に当たる場合にはどうしたらよいのでしょうか。
利益相反取引は禁止されているわけではない
利益相反取引に当たるからと言って、会社法で利益相反取引そのものが禁止されているわけではありません。
ただ、法人が不利益を被らないよう、利益相反取引を行う場合は事前に取締役会または株主総会の承認を得なければならない、という条件が付いているのです。
また承認を得る以外にも以下のように必要な手続きがあります。
利益相反に当たる不動産売買を行う場合の手続き
利益相反取引に当たる不動産売買を行う場合に必要な手続きを、以下でご説明します。
時価で不動産売買取引を行う
法人所有の不動産を取締役が時価より低い価格で購入する場合や、取締役所有の不動産を法人へ時価より高い価格で売却する場合は、法人に不利益が生じます。
このため、不動産売買においては時価相当額で取引するのが基本です。
また、法人から取締役へ時価より低い価格で売却した場合は、時価と売却価格の差額分を売主から買主へ贈与したものと見なされ、法人税や贈与税の対象となることもあるので注意しましょう。
取締役会または株主総会で承認を得る
不動産売買が利益相反取引に当たる場合、取締役会が設置されている会社の場合は取締役会で、そうでない場合は株主総会で承認を得なければなりません。
その際、対象不動産、売買予定金額、売買契約予定日、取引当事者(売主・買主)を明示した上で承認を得ます。
既に売買契約書が用意してある場合は、契約書を提示するとスムーズです。
承認を得られたら、会社法の規定に基づき取締役会議事録または株主総会議事録を作成し、承認があった旨明記します。
この議事録は売買契約後に所有権移転の不動産登記申請を行う際に必要となるので必ず作成しましょう。
また、不動産売買に当たって金融機関から融資を受ける場合は、金融機関からも当該議事録の提出を求められる場合があります。
なお、取締役会が設置されていない会社では、株主総会議事録の代わりに株主全員の書面による同意でもよいとされています。
この場合は株主全員の印鑑証明書を添付した同意書を提出する必要があります。
取締役会設置会社においても一定の要件の元、取締役全員の書面による同意でもよいとされています。
取締役会議事録または株主総会議事録を作成する際は、
- 会社法上の規定に従っているか
- 不動産登記手続きにおける添付書類として提出するのに使える様式であるか
などに留意しましょう。
取締役会議事録を例に取ると、会社法で「不動産取引に関与した取締役は決議に加わることができない」ことや「署名または記名押印の義務」がある者の範囲が定められ、不動産登記法で「議事録の作成者が記名押印し作成者の印鑑証明書を添付」することが定められています。
印鑑証明書は、代表取締役は会社の実印を押印した印鑑証明書を、その他の取締役は個人の実印を押印した印鑑証明書を添付するものとされています。
また、印鑑証明書は期限の定めがないので、過去3か月以内に発行されたものでなくてもかまいません。
なお、取締役・株主が同一人物で1人の場合でも、登記実務上の都合で株主総会議事録が必要とされます。
登記簿には株主が記載されないので、登記官はその会社の株主が1人だけなのか判別できないためです。
売買契約を締結する
承認を得られたら売買契約に進みます。この際、必ず書面で売買契約書を作成します。
不動産登記を行う
不動産売買契約が成立したら登記手続きです。
所有移転登記などの登記申請を行うために必要な書類を揃えます。
たとえば、取締役が法人に不動産を売却する利益相反取引の場合、会社側と取締役側が揃える必要のある書類は以下のとおりです。
<買主の会社側>
- 取締役会議事録または株主総会議事録
- 印鑑証明書(取締役会の場合は出席した役員全員の印鑑証明書が、株主総会の場合は会社の印鑑証明書が必要)
- 会社の登記事項証明書(「全部事項証明書」が必要。)
<売主の取締役側>
- 対象不動産の登記済証(いわゆる「権利済証」)
- 個人の実印の印鑑証明書(過去3ヶ月以内に発行されたもの)
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどいずれか1点)
所有権移転登記が完了したら、法人名義の登記済証が発行されます。
承認を得ずに利益相反取引を行ったらどうなる?
利益相反取引を行うには上記のような手続きが必要になります。
もし、取締役会や株主総会の承認を得ずに利益相反取引が行われた場合、会社側は取引の無効を主張でき、取締役は損害賠償責任を負う可能性があります。
会社側は取引の無効を主張できる
ただし、取引に第三者が関与している場合は、取引が無効になることによりその第三者が不利益を被らないよう、法人が以下のことを主張または立証できる時のみ取引の無効を主張できます。
- 第三者は取引が利益相反取引に該当するにも関わらず承認を得ていないということを知っていた
- 利益相反取引に当たることを第三者が知らなかった場合でも、知らなかったことに重大な過失(落ち度)があった
取締役が損害賠償責任を負うこともある
利益相反取引が原因で法人に実際に損害が生じた場合、取引に関与した取締役は会社に対して損害賠償責任を負うことになります。
なお、法人の承認を得て行った利益相反取引についても、法人に損害が生じた場合は取締役が損害賠償責任を負います。
またこの場合、取引に関与した取締役だけでなく、承認決議に参加した他の取締役も過失がないことを証明できない限り、損害賠償責任を負うことになります。
利益相反に当たる不動産売買を行う場合は専門家に相談しよう!
いかがでしたでしょうか。
この記事では利益相反の意味、利益相反取引の種類、不動産売買における利益相反取引の例を挙げ、不動産売買が利益相反に当たる場合の手続きについてご説明しました。
利益相反取引は会社法で禁止されているわけではありませんが、あらかじめ取締役会または株主総会の承認を得る必要があります。
また手続き上、取締役会や株主総会の議事録作成が必須で、承認後売買を行う際も書面での売買契約書の作成が必須となります。
取締役から法人への無償贈与など、明らかに会社の不利益にならない取引は利益相反取引に当たりません。
ただ、利益相反取引に当たるのか曖昧なケースもあり、必要な手続きや書類もケースによって異なります。
利益相反取引に当たりそうな不動産売買を行う場合は、専門家に相談することをお勧めします。
税理士事務所や司法書士事務所などの他、不動産会社も利益相反取引について相談に乗ってくれる場合があります。
おすすめの不動産会社を紹介していますので下記も是非ご覧ください。