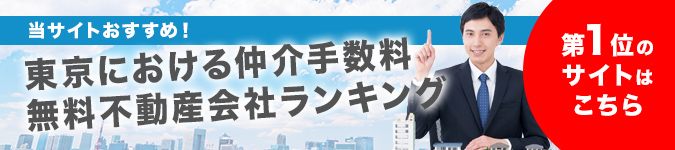家を売却すると税金がかかりますが、その種類と金額はどのようなものがあるでしょうか。
税金は特例や控除の活用で節税につなげることもできます。
家を売却する際の税金を知っておくと、売却費用も含めたトータルの金額で売却の検討も可能です。
今回の記事では家売却時の税金の種類と、節税につながる特例や控除についても詳しく解説していきます。
家売却時の税金で後悔したくない人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
家を売却する際にかかる税金について
家を売却する際にかかる税金は、必ず発生するものと条件によって発生するものがあります。
具体的には以下の表の内容になります。
| 条件 | 税金の種類 |
|---|---|
| 必ず発生する | 印紙税 |
| 消費税 | |
| 場合によって発生する | 譲渡所得税 |
| 登録免許税 |
それぞれの税金の内容について順番に解説していきます。
必ず発生する税金「印紙税」
不動産取引の際に売買契約書に貼り付けする印紙が印紙税となります。
決められた金額の印紙を購入して、貼り付けすることで納税したと見なされます。
売買取引の金額によって、印紙の金額がそれぞれ以下の表のように定められています。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される契約書については、上記の軽減税率が適用されます。
必ず発生する税金「消費税」
不動産会社や司法書士、金融機関に業務を依頼した場合に発生する手数料には消費税がかかります。
手数料の具体例としては、不動産会社の仲介手数料や司法書士へ支払う書類作成の手数料、金融機関の融資手続きの手数料などがあります。
これらの手数料に対して10%の消費税が必ず発生します。
消費税の支払いをせずに売買取引を進めたい場合は、不動産会社を通さずに直接個人で取引を行う方法があります。
しかし、不動産取引には多くの専門知識を必要とするため、個人取引はおすすめとは言えません。
消費税はかかりますが、専門家に依頼するのがトータルで考えた場合メリットがあると言えるでしょう。
場合によって発生する税金「譲渡所得税」
家を売却した金額が、購入したときの金額を上回った場合に出る利益を譲渡所得といいますが、その譲渡所得にかかる税を譲渡所得税といいます。
譲渡所得税は、所得税、住民税、特別復興所得税の3つの税を合わせた総称です。
譲渡所得が発生しないと譲渡所得税はかかりませんので、必ずかかる税金ではありません。
譲渡所得税は売却金額に税率をかけて計算され、売却時にかかる税金としてはもっとも大きな金額となります。
場合によって発生する税金「登録免許税」
不動産を売却する際に名義変更を行ったり、住宅ローンの抵当権を抹消したりする場合には登録免許税がかかります。
以下の表のように申請内容によって税額は異なります。
| 申請内容 | 税額 |
|---|---|
| 名義変更 | 固定資産税評価額×2.0% |
| 抵当権の抹消 | 1,000円 |
名義変更の登録免許税については、一般的に買主が支払うことが多いです。
抵当権の抹消については、建物と土地をそれぞれ別の不動産として考えるので一戸建ての住宅の場合、合計2,000円がかかるので注意しましょう。
家売却時の譲渡所得税の計算方法
前項で説明したとおり家を売却した際に利益が出ると、所得税、住民税、復興特別税などの譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は、家の売却価格だけでなくさまざまな要素によって決定します。
譲渡所得税の計算方法について詳しく解説していきましょう。
まずは譲渡所得の計算が必要
譲渡所得税を計算するには、まずは譲渡所得を確認することが必要です。
譲渡所得は家を売却した際の利益になりますが、単純に購入価格と売却価格の差額で求められるというわけではありません。
譲渡所得税の計算式は以下になります。
| 譲渡所得 = 譲渡価格 – (取得費用 + 譲渡費用) |
譲渡価格は家の売却価格、取得費用は家の購入価格と購入時の諸費用を足したもの、譲渡費用は売却時の諸費用になります。
それぞれの費用の求め方について確認していきましょう。
家の譲渡価格を確認する
家の譲渡価格とは売却価格のことです。
不動産会社に仲介を依頼して売買契約を結んだ場合は、売買契約書に明記されているので確認してみましょう。
これから売却を検討している方はおおよその価格を予想して計算するとよいのですが、不動産会社に査定を依頼すると正確な金額を算出してくれます。
無料で相談できるので、不動産会社に査定を依頼してみるのも1つの方法です。
家の取得費用を確認
家の取得費用は土地、建物の購入価格だけではなく、手数料や諸費用も含めた購入に関わる費用全般になります。
取得費用として見なされる費用としては以下のようなものがあります。
- 土地、建物の購入代金
- 仲介手数料
- 不動産取得税
- 契約書の印紙税
- 登記費用
- リフォーム費用
- 免許登録税
- 登記手数料
- 住宅ローン事務手数料
- 住宅ローン保証事務手数料
- 建築費、工事費
建物については時間の経過によって価値が減少していく為、原価償却を行って取得費用を算出する必要があります。
以下の計算で求めた償却費を、もとの購入代金から差し引いて算出します。
| 原価償却費 = 建物の購入価格 × 0.9 × 償却率 × 経過年数 |
償却率は建物の種類によって決まっていて、さらに居住用と事業用でも異なる値が設定されています。
以下は居住用の建物の主な償却率になります。
| 建物の構造 | 耐用年数 | 償却率 |
|---|---|---|
| 木造 | 33年 | 0.031 |
| 軽量鉄骨 | 40年 | 0.025 |
| 鉄筋コンクリート | 70年 | 0.015 |
上記をもとに家の取得費用を確認していきましょう。
家の譲渡費用を確認
家の譲渡費用は土地、建物を売却するためにかかった諸費用の合計になります。
家売却時の諸費用としては以下のようなものが含まれます。
- 仲介手数料
- 契約時の印紙税
- 建物の取り壊し費用
- 立ち退き料(賃貸の場合)
目安として譲渡費用は売却価格の5%ほどになります。
譲渡所得税の計算方法について
前項で求めた譲渡所得に税率をかけることで、譲渡所得税の計算ができます。
| 譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率 |
税率については、家を所有していた期間によって変わってきます。
家の所有期間によって税率が変化
譲渡所得税の税率は家の所有期間が5年を過ぎると変化します。
長く所有していた方が税金としてはメリットがあり、短期と長期で以下のように分類されます。
| 種類 | 家の所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% |
短期譲渡所得は家の所有期間が5年以下の場合で、税率は39.63%です。
税率の内訳としては、所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%となっています。
家の所有期間が5年を超えると、長期譲渡所得となり税率が20.315%になります。
税率の内訳は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%です。
注意点としては、所有期間を判断する基準が家を売却した年の1月1日時点になるということです。
例えば、2015年3月1日に購入した不動産を2020年4月1日に売却した場合、実質は5年以上たっていますが判断基準は2020年1月1日となります。
所有期間は4年間と見なされてしまうので区分としては短期譲渡所得になるわけです。
税率が大きく変わってしまうので、売却の時期は注意して見きわめましょう。
家売却時の税金を抑える控除と特例について
家を売却した際に利益が出ると税金がかかりますが、条件を満たせば控除や特例を受けられ負担を軽くできます。
具体的にどのような控除や特例の適用があるのか、内容について順番に解説していきましょう。
家売却時は3,000万円特別控除が適用
家を売却した際には所有期間にかかわらず、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
この控除を適用した場合、税額の計算は以下のようになります。
| 税額 = (譲渡所得 - 3,000万円) × 税率 |
すなわち譲渡所得が3,000万円を超えないかぎり、税額は0円となるわけです。
適用条件としては、以下の項目があります。
- 家に住まなくなってから3年以内に売却
- 他の土地を活用して利益を得ていない
- 直近3年間でこの控除を利用していない
- 売手と買手が親子や親族などの特別な関係ではない
- 買い替え特例や住宅ローン控除との併用不可
3,000万円特別控除は家の所有期間によらないため、ほとんどの方が受けられる控除と言えるでしょう。
家の所有期間に応じた軽減税率
家の所有期間が10年を超えると軽減税率が受けられるようになり、長期譲渡所得よりも低い税率で譲渡所得を計算することができます。
| 課税譲渡所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 14% |
| 6,000万円超の部分 | 20%(通常の税率) |
通常だと税率は所得税15%、住民税5%の合計20%ですが、軽減税率が適用できると所得税10%、住民税4%の合計14%となります。
課税譲渡所得が6,000万円を超える部分については通常の税率です。
3,000万円特例控除と併用して適用することができるので、さらに節税することが可能となります。
こちらも1月1日時点での所有期間で判断されますので注意しましょう。
家の買い替え時に使える特例
家を買い替える際に、条件によっては「特定の居住用財産の買換えの特例」が使用できます。
これは譲渡所得税の課税タイミングを先へ延ばすことができるという特例です。
譲渡益が非課税になるわけではないので注意しましょう。
特定の居住用財産の買換えの特例適用条件には以下のものがあります。
- 家の売却代金が1億円以下
- 3,000万円特別控除などの特例を過去3年間受けていない
- 売却する家の居住期間と所有期間がともに10年を超えている
譲渡損失があった時の特例
家を購入した金額より売却した金額が少ないと売却損となりますがこの損失額を譲渡損失といいます。
譲渡損失があった際に使える特例が、「居住用不動産の譲渡損失の損益通算」です。
損失分を他の所得から差し引くことができるので、課税金額が下がり税金を安くおさえることができます。
さらに、控除しきれなかった場合でも最大3年間は繰り越すことができるのが特徴です。
適用の条件としては以下を満たしている必要があります。
- 個人が有する土地、建物であること
- 1月1日における不動産の所有期間が5年超
- 売却相手が配偶者など直系の親族ではない
- 適用年の所得3,000万円以下
- 直近3年間ほかの特例を利用していない
- 10年以上住宅ローン期間が残っている
家売却時の税金の注意点
家を売却する際の税金は特例や控除が適用できますが、気を付けなければいけない点もいくつかあります。
税金を支払うタイミングや計算時の注意点を順番に解説していきましょう。
売却時の控除と住宅ローン控除は併用不可
家を売却する際の特例と控除について説明してきましたが、新しい家を購入する際の住宅ローン控除と併用できないことがあります。
以下の特例については、住宅ローン控除と併用ができません。
- 3,000万円特別控除
- 所有期間10年超の家売却時の軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換え特例
家を買い替えるために売却する際は、利用する控除を比較検討する必要があるでしょう。
どの特例がもっとも節税になるか気になるところですが、住宅ローン控除が節税額としては大きくなることが多いです。
新しく住む家を賃貸にして、2年以上経過してから新居にすれば住宅ローン控除も利用できるのでひとつの方法として参考にしてください。
取得費用が不明な場合の計算
売却する家が相続した家などの場合、購入時の金額が分からないこともあるでしょう。
そのような場合は、売却する金額の5%を取得費として見なすことができます。
売却金額が2,000万円の家の場合、取得費は100万円として見なされます。
また、実際の取得費が5%を下回る場合でも5%相当を取得費とすることも可能です。
控除には確定申告が必要
家を売却した際の税金の特例や控除を利用するには、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行うのは、家を売却した翌年の2月16日から3月15日までとなります。
家を売却したタイミングによっては確定申告までに時間が空いてしまうので、忘れないように気を付けましょう。
確定申告の提出先は、新しい家の所在地ではなく住民票がある住所の税務署となりますので注意が必要です。
申告の内容や必要書類について不明点があれば、税務署で相談することも可能です。
1月からは混み合うことが多いので、早めの準備をおすすめします。
税金以外にも費用が発生する
今回、家を売却する際にかかる税金について解説してきましたが売却時には税金以外にも費用が発生します。
とくに金額が大きなものとしては、不動産会社に支払う仲介手数料があげられます。
売却価格の4%程度を支払う必要がありますので覚えておきましょう。
家売却でかかる税金をシミュレーションで解説
実際に家の売却でどれくらいの税金がかかるか、特例や控除でいくら節税できるのかシミュレーションしてみましょう。
【売却する条件】
- 新しく購入するのは新築戸建て(木造、居住用)
- 購入額:3,500万円
- 売却額:6,000万円
- 譲渡費用:100万円
- 居住期間:16年
(1)譲渡所得を計算する
まずは取得費用を確認するために、建物の原価償却を反映させます。
|
原価償却費 = 3,500万円(購入額) × 0.9 × 0.031 × 16年(居住期間) = 1,562万円 |
購入額から原価償却費用を差し引くと取得費用が求められます。
| 取得費 = 3,500万円(購入額) – 1,562万円(償却費) = 1,938万円 |
次に譲渡所得を計算します。
|
譲渡所得 = 6,000万円(売却額) – 1,938万円(取得費) -100万円(譲渡費用) = 3,962万円 |
(2)特例、控除を適用して課税譲渡所得を計算する
3,000万円特例控除を適用して譲渡所得から差し引きます。
| 課税譲渡所得 = 3,962万円(譲渡所得) – 3,000万円(特例控除) = 962万円 |
(3)課税譲渡所得に税率をかけて税金を計算する
最後に税率をかければ税金が計算されます。
今回は居住期間が10年を超えているので長期譲渡所得よりも低い税率が適用されます。
この軽減税率は3,000万円特例控除と併用が可能です。
| 譲渡所得税 = 962万円(課税譲渡所得) × 14.315% = 137.7万円 |
以上から、シミュレーション結果として家の売却で137.7万円の税金がかかることが分かりました。
まとめ
家を売却する際に利益が出ると、税金がかかります。
それぞれの税金について解説させていただきましたが、シミュレーションの内容とあわせて確認することでよりイメージしやすくなるはずです。
シミュレーション結果では特例や控除を適用したとはいえ、100万円以上税金を支払う必要があることが分かりました。
家は購入時だけではなく売却時にも大きなお金がかかります。
不動産に関する税金の仕組みを理解して、税金や売却費用も含めて売却価格を検討していきましょう。