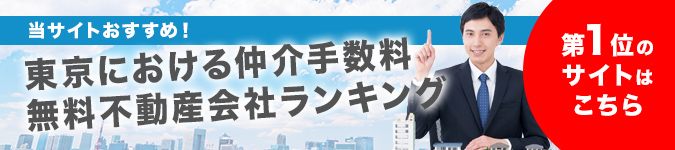知人間で不動産売買を行う場合など、個人間での契約がしばしば行われます。
仲介業者を介した場合、価格交渉や契約書の作成など、必要手続きを任せることができますが、個人間での取引では全てを自分たちで行わなければなりません。
当記事では、「不動産の個人間取引を検討している」「個人間での不動産売買契約書を作成したい」という方へ向けて、不動産売買契約書の作り方、個人間での不動産契約での注意点についてご紹介します。
目次
そもそも個人間での不動産売買は可能?
「個人間で不動産の売買ってできるの?」とお思いの方も多くいらっしゃるかと思います。
結論からいうと、個人間での不動産売買は可能で、法律的にも合法的な取引となります。
また、個人間での不動産取引は仲介業者を介する場合と違い、宅地建物取引士免許など、国家資格も必要ありません。
不動産業者を介しての不動産取引は、「売買契約書」「重要事項説明書」を不動産業者が作成し、宅建士が記名・捺印して重要事項説明を行うことが義務付けられていますが、個人間ではこのような義務はありません。
民法上では、契約書がない口約束でも不動産取引は成立します。
そのため、個人間での不動産売買で行う全てのことは自己責任となります。
制約が設けられていないからこそ、個人間での不動産売買取引は様々な知識が必要になります。
しかし、口約束でも不動産の取引が可能であるからといって、契約書を作成せず売買を行うことはトラブルに繋がりやすく、大変リスキーです。
不動産を売却・購入する際は、個人間であっても必ず契約書を作成しましょう。
個人間で不動産売買を行うメリット
個人間での不動産売買は全て自分で取引を行わなければならないため、知識のない人にとっては、不動産業者を介する時よりも大変な作業になります。
そんななかでも、実際に個人間での不動産売買に魅力を感じ、取引を行なっている人がいるのも事実です。
本章では、個人間での不動産売買のメリットをご紹介します。
仲介手数料がかからない
個人間の不動産売買での一番のメリットは、不動産仲介手数料がかからないというところです。
不動産仲介業者を介した場合にかかる手数料は下記となります。
| 物件の売買価格(税抜) | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 400万円超 | 売買価格(税抜)×3%+6万円(+消費税) |
| 200万円〜400万円以下 | 売買価格(税抜)×4%+2万円(+消費税) |
| 200万円以下 | 売買価格(税抜)×5%(+消費税) |
仮に4,000万円の物件を取引した場合、不動産業者に支払う仲介手数料は税抜で126万円となります。
個人間での不動産売買取引では、このような仲介手数料を支払う必要がありません。
初期費用としてかかる仲介手数料を浮かせることができる点が、個人間売買のもっとも大きな利点です。
個人間ならではの自由が効く
個人間での不動産売買は、不動産業者を介することがないため、当事者同士だけの意思決定で全ての取引を行うことができます。
また、個人間での取引は親戚や知人など、知り合いが契約相手であるパターンも多くあります。
契約条件や売却価格など制限なく、全て自由な取引ができるところが、個人間での不動産売買のメリットです。
個人間で不動産売買を行うデメリット
取引の自由度が高く、仲介手数料などの費用をカットできるところが魅力的な個人間での不動産売買取引。
魅力的である一方で、具体的にはどのような点が大変になるのでしょうか?
ここからは、個人間の不動産売買を行う上でのデメリットをご紹介します。
手間がかかる
個人間不動産売買のデメリットは、なんといっても手間がかかる点です。
個人間で取引を行う場合、売買契約書の作成だけではなく、所有権移転の登記手続き、住宅ローンを考えている場合はその融資先との連携など、本来不動産業者がやってくれることを全て自分たちで行わなければなりません。
そのため、プロの不動産業者が資格を取得して慎重に行なっている取引を、個人だけの力で行うことは容易ではない事を認識しておきましょう。
また、個人間での不動産売買取引では、重要事項説明書を交付する必要がありませんが、買主が住宅ローンを受けたい場合には重要事項説明書が必要となります。
金融機関は、物件の詳細が掲載されている重要事項説明書を元に融資を決めているので、融資を受ける際は重要事項説明書が必須となるのです。
しかも、宅地建物取引業法という法律により、重要事項説明書は宅地建物取引士にしか作成できない事になっています。
その場合、結局個人での不動産売買取引をサポートしている不動産会社を探して、作成してもらわなければならない可能性もあることを覚えておきましょう。
トラブルがつきもの
前述した通り、契約書の作成しかり、個人間での不動産の売買は様々な取引を当事者だけで行うことになります。
複雑な不動産の取引を専門家のサポートなしで行うことになるため、事前の価格設定で揉める、契約書に不足事項があった、引渡後に物件に瑕疵が見つかったなど、仲介者がいないからこそ起こるトラブルが数多く考えられます。
個人間での不動産売買取引は、契約書を作成してハンコを押したら終わり、という簡単なものではありません。
多くのトラブルを防ぐためにも、不動産に詳しい方以外には、個人間取引はあまりおすすめできないというのが実情です。
不動産売買契約書の作り方
ここから、個人間取引での不動産売買契約書の作り方をご紹介します。
不動産売買契約書とは、不動産取引を行う際の取り決めを記載しているものです。
仲介や個人間など、取引の形態に関わらず、契約書に記載してある内容は基本的に同じです。
記載してある内容としては、下記となります。
- 売買物件の表示
- 売買代金、手付金の額、支払い期日
- 土地の実測及び土地代金の精算
- 所有権の移転と引き渡しの時期
- 付帯設備等の引継ぎ
- 抵当権等の抹消
- 公租公課等の精算
- 手付解除の期限
- 契約違反による解除
- 引き渡し前の物件の滅失・毀損
- 反社会勢力の排除
- ローン特約
- 契約不適合責任
ひとつずつ、簡単に解説していきます。
売買物件の表示
売買する不動産についての情報を記載します。
物件情報は法務局にて取得できる登記簿謄本で確認できます。
ちなみに、地番と住居表示は異なるものです。
住居表示とは、一般的な住所のこと。地番とは、土地の番号として、登記簿謄本に掲載されている情報を指します。
混ざってしまわないように気をつけましょう。
売買代金、手付金の額、支払い期日
売主・買主で決めた売買価格や支払い期日を記載します。
もし手付金がある場合は、手付金の額とその支払い日も記載しておくようにしましょう。
手付金の一般的な相場は売買代金の5%〜10%とされています。
また、不動産業者が売主の場合、手付金は売買代金の20%以内、かつ、売買契約の解除をすることができる手付金「解除手付」である必要がありますが、個人間での不動産売買では特に定めはなく、自由に設定できます。
売買代金や手付金などの取り決めは、売主が主導権を握ってしまうと、買主に不利になることもあり得ますので、買主は慎重に取引を進めましょう。
土地の実測及び土地代金の精算
個人間の取引では、契約前に必ず、取引を行う土地の実測を行うようにしましょう。
登記簿謄本に記載されている土地の面積と、実際の土地の面積は異なる場合があります。
そのため、「土地を購入して新たに物件を建てるつもりだったのに、いざ実測してみたら登記簿謄本よりも面積が小さくて建物が建てられなくなってしまった…」なんてこともあり得ます。
売主は契約前に必ず実測を行いましょう。また、土地面積に誤差があった場合に売買代金の増減をするのか否かについても、ここで事前に取り決めておきます。
所有権の移転と引き渡しの時期
一般的に、不動産売買取引では、所有権の移転と引き渡しは同日に行われます。
買主は、支払いが完了した時期ではなく、所有権移転手続きを完了したタイミングで第三者に所有権を主張できるようになります。
引越しなどのスケジュールを加味したうえで、売主・買主双方が納得するタイミングで所有権の移転時期・引き渡しの時期を決めるようにしましょう。
付帯設備等の引継ぎ
中古マンション・中古戸建など、中古物件の売買契約を行う場合、エアコンや照明・インターホンなど、各種付帯設備のなにを引き継いで、なにを撤去しておくのかを契約時に決めておきます。
また、その付帯設備は問題なく使用できるものなのか、故障している箇所があればその旨も売主・買主で確認しておくと、今後のトラブルを防ぐことができます。
「問題なく使えると思っていた設備が実は故障していて、修理に多額のお金がかかった」といった場合、誰が修理費用を支払うのか揉めてしまう可能性もありますので、しっかりと契約時にすり合わせをしておきましょう。
抵当権等の抹消
売主は契約前に、抵当権や先取特権・地上権など「買主の所有権の行使を阻害するような負担」を抹消しなければなりません。
これらの権利を抹消した旨を確認し、契約書に記載しておきましょう。
公租公課等の精算
公租公課とは、固定資産税・都市計画税などの、国や地方公共団体に納める税金のことを指します。
これらの税金は、毎年1月1日に所有権のある人に課せられるものであり、所有権が移転したタイミング(=引き渡しの日)を基準として日割り計算を行い、買主から売主へ精算を行う必要があります。
手付解除の期限
手付金がある場合は、手付解除の期限、すなわち、「契約を解除する場合、いつまで手付解除が有効なのか」について設定しておきます。
また、手付解除はできない、と設定することも可能です。
契約違反による解除
売主、または貸主のどちらかが契約違反をした場合の契約解除方法や、違約金の取り決めを記載します。
一般的には、違反を行った者が違約金を支払うことで契約解除とし、違約金は売買代金の20%相当額となることが多いです。
引き渡し前の物件の滅失・毀損
引き渡し前に、地震などの天災地変で、売主・買主の双方の責任のないところ、不可抗力で物件が滅失・毀損した際の取り決めを記載します。
「まさかそんなこと起こらないだろう」と思われるかもしれませんが、自然災害はいつどこで起こるかわかりません。
トラブルを防ぐためにも、天災地変が起こった際には売主が修復した上で物件を引き渡す・物件の修復が不可能なレベルである場合は契約解除とできるなど、しっかりと話し合っておきましょう。
反社会勢力の排除
売主・買主のどちらかが反社会勢力と関わりがある場合、契約を解除できると定めるものです。
一般的には、反社会勢力との関わりが判明した場合、催告など無しに契約を解除することができます。
ローン特約
買主が住宅ローンを組む場合のみ記載します。
一般的に、金融機関から住宅ローンを受けることができなかった場合、契約は白紙となります。
前述した通り、住宅ローン審査で必要となる重要事項説明書は宅建士が作成するものですので、買主が住宅ローンを受ける際には不動産業者の介入が必須となります。
契約不適合責任
「契約不適合責任」とは、引き渡しが完了した後に、契約書の内容と異なる点が見つかった際、売主が負担する責任の範囲について決めておくものです。
以前まで「瑕疵担保責任」と呼ばれていたもので、2020年4月の民法改正により「契約不適合責任」という名称に変更になりました。
「瑕疵担保責任」で売主が買主に追求できた契約解除権・損害賠償請求権に加え、追完請求権・代金減額請求権をできるようになりました。
責任を負う期間が長ければ長いほど、売主は不利となり、買主は有利となります。
引き渡し後の不備についてはトラブルが起こりやすいポイントですので、しっかりと決めておきましょう。
不動産売買を個人間で行う際の注意点
「メリット・デメリットを確認したうえで、それでも個人間で不動産売買を行いたい!」という方へ向けて、取引を行う上での注意点や、円滑に取引を進める上でのポイントをご紹介します。
実際に個人間取引を行う際は、以下の3点を視野に入れて動き出していきましょう。
契約不適合責任について
前述した通り、契約不適合責任とは、引き渡し完了後に契約内容と異なる点が見つかった際の、売主が負担する責任の範囲のことです。
2020年の民法改正により、買主が売主に請求できる権利が増え、売主の責任が重くなりました。
契約不適合責任はその名の通り、契約に適しているかどうかで責任が発生します。
すなわち、契約書に書いていたか否かがポイントとなるのです。
物件に瑕疵がある場合はきちんと契約書に記載し、その瑕疵に対して契約不適合責任対象とするのか否か、契約不適合責任を全て免責にするのか否か、契約不適合責任で買主が請求できる権利のうち、全て請求可能とするのか一部のみ請求可能とするのか、など個人間での不動産売買では特に揉めやすいポイントなので、ひとつひとつ双方で確認し慎重に進めるようにしましょう。
必要書類を確認する
不動産売買取引を円滑に進めるために準備しておくべき書類は、一般的に売主の方が多くなります。
法務局や市役所などで、必要書類を事前に集めておきましょう。
売主が準備しておくもの
- 登記済証または登記識別情報
- 実印
- 印鑑証明書
- 建築確認通知書
- 固定資産税納税証明書
- 印紙代
- 免許証などの本人確認書類
買主が準備しておくもの
- 印鑑
- 手付金(必要な場合のみ)
- 印紙代
- 免許証などの本人確認書類
仲介業者に依頼する選択肢を視野に入れておく
ご紹介してきた通り、個人間での不動産売買は非常に複雑な取引となります。
不動産の知識が豊富な方ならば、個人間での取引を行なっても良いかと思いますが、そうではない場合は不動産業者へ仲介を依頼することも視野に入れておくことを強くおすすめします。
不動産業者を介する際に一番ネックと言える仲介手数料ですが、なかには仲介手数料無料の不動産業者も存在します。
また、不動産業者を介することで、契約時だけではなく、そのほかの各種手続き・引き渡し後のアフターサポートも受けることができます。
トラブルを減らすために、そしてなにより、安心して不動産取引を行うために、プロのサポートを受けることも重要です。
以下のサイトでは、沢山の仲介手数料無料の不動産会社を紹介しております。
中でも、オススメの仲介手数料無料の不動産会社は「株式会社リアル」です。
購入時だけではなく売却時にも最大仲介手数料が無料になる不動産会社です。
仲介手数料が発生するのを気にされる場合には、ぜひご覧ください。
まとめ
個人間での不動産売買について、不動産売買契約書の作り方や、気をつけておくべきポイントについてご紹介してきました。
いかがでしたでしょうか?
契約書一つ作成するにも複雑な内容が多く、驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。
個人間での不動産売買は一筋縄ではいきません。
売主・買主、双方が納得のいく不動産売買を行うことができるよう、しっかりと事前準備をして、契約に臨みましょう。