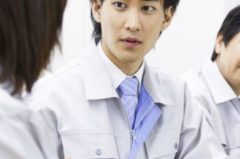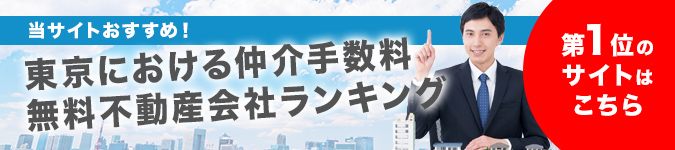インターネットの普及などにより不動産市場がオープンになり、地元の不動産屋さんだけが物件情報を握る時代ではなくなりました。
不動産の購入を検討する際、インターネットの不動産ポータルサイトなどで物件を探す人も増えています。
ポータルサイトで物件を検索すると、複数の不動産会社が同じ物件の広告を出しているのを見かけたことはないでしょうか。
それはなぜなのか、その理由と不動産会社を選ぶ時のポイントを解説します。
目次
同じ物件を複数の不動産会社が扱っていることがある
次のような場面で、複数の不動産会社が同じ物件を扱っているのを見かけることがあります。
不動産ポータルサイトに同じ物件が並んでいる
多くの不動産ポータルサイトで不動産を検索すると、同じ物件がずらりと並び、かつそれぞれ別の不動産会社が広告を出していることがよくあります。
複数の不動産会社が同じ物件を宣伝・紹介している
たとえば中古マンション等の購入を検討している方が複数の不動産会社に相談したところ、同じ物件を紹介される、または複数の不動産会社のウェブサイトに同じ物件が表示されている、といったケースもあります。
なぜ複数の不動産会社が同じ物件を扱っているの?
同じ物件を複数の不動産会社が扱っているのはなぜでしょうか。
それは、不動産取引の仕組みに基づく以下の2つの理由によるものです。
不動産会社は物件情報を共有している
売主側の不動産会社は、仲介を依頼されたら不動産会社が情報を共有する「レインズ」というプラットフォームに物件情報を掲載します。
プラットフォームを通じて不動産会社間で物件情報が共有され、その結果、複数の不動産会社が買主を探すために同じ物件の広告を出すのです。
「レインズ(REINS)」は「Real Estate Information Network System」の略称で、「不動産流通標準情報システム」のことです。
レインズは国土交通大臣から指定を受けた東日本、中部、近畿、西日本の4つの不動産流通指定機構により運営されており、一般には公開されておらず不動産会社(宅地建物取引業者)だけが閲覧できます。
売主が複数の不動産会社に売却を依頼している場合
売主側が複数の不動産会社に仲介を依頼している場合は、それぞれの不動産会社が売主のために同じ物件の広告を出すことになります。
売主側が複数の不動産会社に仲介を依頼することは、以下でご説明する「媒介契約」の種類により可能です。
不動産仲介業の仕組み
不動産の「仲介業務」とは、国や都道府県が発行する「宅地建物取引業免許」を有する不動産会社が、不動産取引に当たって売主や買主の仲立ちをする業務です。
売主側の不動産会社は物件の広告を出して買主を探し、買主側の不動産会社は希望条件に合う物件を探します。
また、購入希望者が現れたら物件の「内覧」時に立ち会い、契約条件の調整、契約締結、物件の引き渡しまで、売主または買主を総合的にフォローします。
不動産媒介契約には3種類ある
売主側の仲介業務は、売主側と不動産会社が「媒介契約」を締結した時にスタートします。
媒介契約は下の表のとおり3種類。この内、「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」を結んだ場合、売主側は不動産会社1社としか媒介契約を締結できません。
一方、「一般媒介契約」を結んだ場合は複数の不動産会社と契約締結することができます。
媒介契約の種類
| 媒介契約の種類 | 複数の不動産会社と契約 | 自己発見取引 | 指定流通機構への登録義務 | 売主への業務報告 | 契約の有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 可 | 可 | 任意 | 任意 | 指定なし |
| 専任媒介契約 | 不可 | 可 | 7営業日 | 2週間に1回以上 | 3ヶ月以内 |
| 専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 | 3ヶ月以内 |
※「自己発見取引」は売主が自ら買主を見つけて売買契約を締結すること
売主と専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んだ不動産会社は、売買が成立すればほぼ確実に仲介手数料を受領できる分、レインズへの登録や売主への業務報告に関して厳しい義務が課されています。
一方、複数の不動産会社に依頼することができる「一般媒介契約」の場合、他社が買主を見つけた場合は自社に仲介手数料が入りません。
不動産会社が指定流通機構に物件を登録するのは任意であるなど、不動産会社へ課される義務が厳しくありません。
売主側の不動産会社と買主側の不動産会社がいる
不動産仲介においては通常、売主側の不動産会社と買主側の不動産会社の2社が介在します。売主側の不動産会社は物件の販売活動を、買主側の不動産会社は買主の希望条件に合った物件を探します。
ただし、単独の不動産会社が売主側と買主側のそれぞれと媒介契約を結ぶ場合があり、売買が成立した暁には、その不動産会社は売主と買主の双方から仲介手数料を受け取ることができます。このケースを業界用語で「両手取引」と言います。
買主と不動産会社の媒介契約はいつ交わす?
買主側の媒介契約はいつ締結するのでしょうか。
実は、買主側は物件を探し始めた時に不動産会社と媒介契約を交わすことはまれです。
買主側が購入を決定して売買契約を締結する段階で、媒介契約も同時に交わすのが一般的です。
不動産会社を選ぶ時のポイント
さて、数ある不動産会社の中から仲介を依頼する不動産をどのように選んだらいいのでしょうか。
一般的に、どの不動産会社を選んでもたいていは大きな差はありません。
ただ、中には買主側よりも売主側にばかり寄り添う不動産会社がいたり、反対に買主側の仲介手数料を値引きまたは無料にしてくれる不動産会社がいたりします。
不動産は一生の買い物。その購入までのプロセスをフォローしてくれる不動産会社は、慎重に選びましょう。
以下で、主に買主側が不動産会社を選ぶ時のポイントを5つご説明します。
誠実な対応をしてくれるか
不動産会社の担当者が物件の特性を十分説明してくれたり、内見希望に快く応じたりしてくれる不動産会社を選びましょう。
買主側に十分な検討の時間を与えずに契約を急いだり、買主側の希望条件に合わない物件を強引に勧めてきたりする場合は、注意しましょう。
買主側に立って考えてくれるか
不動産会社が売主側だけでなく買主側にも寄り添ってくれるかを見極めましょう。
不動産会社が売主側からも仲介を依頼されている「両手取引」の場合、売主側にのみ寄り添う不動産会社も中にはいます。
たとえば、物件やエリアのマイナスポイントも伝えてくれるか、価格交渉など買主側の希望にも真摯に応じてくれるか、などが判断ポイントです。
エリアや物件に詳しいか
もし不動産会社が物件の所在するエリアに詳しくなければ、売り出し価格が適正なのかもわかりませんし、物件自体に詳しくなければ瑕疵に気づかない可能性もあります。
購入を決断するのに十分な情報を得られるよう、エリアや物件に詳しい不動産会社の方が良いでしょう。
不動産に関する専門的知識があるか
不動産の仲介業務を適切に行うには、不動産に関する専門的知識が必要です。
たとえば、周辺相場を把握するには、過去に周辺で取引された不動産の事例を分析した上で、物件の特性、道路条件やエリアの法規制など考慮すべき要因が多数あります。
不動産会社に専門的知識があるかどうかは、担当者が物件等の説明をする時の様子からもある程度分かりますし、その会社に「宅地建物取引士」(以下「宅建士」と言う)が何人いるかも参考になります。
「宅建士」はいわば不動産取引の専門家であり、「宅地建物取引業法」で定める宅地建物取引士資格試験に合格して資格登録した者を指します。法律上、不動産売買契約時に行う「重要事項」の説明は宅建士が行うことと定められています。
宅建士になるための試験には、不動産取引、権利関係に関する法律、不動産にかかる法令上の制限、税金など幅広い分野が含まれ、試験に合格した宅建士は不動産取引に必要な知識を一通り習得していると言えます。
不動産仲介を行う不動産会社は、専任の宅建士を(宅建業に従事する)従業員の5分の1以上置かなければならないとされています。
たとえば10名の事務所であれば、2名以上の宅建士が必要。
不動産会社を選ぶに当たって、法定上の人数より多い宅建士がいる場合はプラスポイントとなります。
仲介手数料の額
「仲介手数料」は、不動産会社が行う仲介業務に対して、売買が成立した時のみ売主・買主が支払う「成功報酬」です。
仲介手数料の額は、同じ物件だとしても依頼した不動産会社によって差が出ることがあります。
仲介手数料はどうやって決まる?
仲介手数料は宅地建物取引業法により「上限」が決められており、以下の簡易計算式により求められます。
【仲介手数料簡易計算式】
(売買金額 × 3% + 6万円) +消費税
法律で定められた仲介手数料の上限額は下の表のとおり。売買金額の200万円の部分が売買金額の「5%と消費税」、200万円超~400万円以下の部分が「4%と消費税」、400万円超の部分が「3%と消費税」になります。
売買金額が400万円超の場合は、これを計算して式をまとめると上記の「仲介手数料簡易計算式」になるのです。
| 売買金額の200万円以下の部分 | 売買金額の5%+消費税 |
|---|---|
| 売買金額の200万円超〜400万円以下の部分 | 売買金額の4%+消費税 |
| 売買金爆の400万円超の部分 | 売買金額の3%+消費税 |
仲介手数料以外の名目で請求される費用
不動産の売買に当たっては、仲介手数料以外にも支払わなくてはならない費用がいくつかあります。
たとえば買主側が仲介手数料の他に支払う費用としては、「印紙税」、「登録免許税」、「司法書士報酬」、またローンを組んで購入する場合は「ローン手数料」がかかります。
なお、「司法書士報酬」は登記業務を行う司法書士へ支払う報酬ですが、司法書士は仲介業務を行う不動産会社から紹介されることが一般的であり、報酬額はケースにより異なります。このため仲介手数料の額と併せて、これらの費用も頭に入れておきましょう。
仲介手数料が安くなる時はある?
上述したように、仲介手数料の額は上限額のみ法律で定められているので、その額以内であればいくらでも良く、無料にすることも可能です。
ただ、これまでは慣行上、仲介手数料の上限額を不動産会社から請求されることがほとんどでした。
ただし、これからは不動産業界も差別化の時代です。
不動産会社の中には、一定の条件の下で仲介手数料を値引きまたは無料にしてくれるところがあります。
仲介手数料が安いとサービスも劣る?
仲介手数料が安いと、不動産会社が提供するサービスの質が劣るのではないかと心配になるかもしれません。
ただ、以下のようなきちんとした理由に基づいて仲介手数料を安くしているのであれば大丈夫でしょう。
不動産会社が売主
不動産会社が物件の売主であれば、そもそも仲介手数料が発生しません。新築建売住宅や新築マンションの販売で多いケース。また、不動産会社が買い取るなどして所有している物件を売り出している場合もこのケースです。
不動産会社の営業努力
ITの普及により、物件の購入を検討する際、必ずしも不動産会社の実店舗に足を運ぶ必要がなくなりました。そこで、IT等を駆使した業務効率化を進め、実店舗の数や広さを抑え少数精鋭で営業している不動産会社などが、仲介手数料の値引きを始めています。
このような会社の中には、仲介手数料の値引きという形だけでなく、プレゼントやキャッシュバックキャンペーンという形で買主に還元するケースもあります。
両手取引で売主のみから受領
不動産会社が売主側・買主側のいずれの仲介も行う「両手取引」では、売買が成立した場合、不動産会社は売主・買主の両方から仲介手数料を受領することができます。昨今では、仲介手数料を主に売主のみから受領し、買主からの仲介手数料を値引きまたは無料にしてくれる不動産会社も出てきました。
途中で不動産会社を代えてもいい?
買主側が途中で不動産会社を代えることは可能です。不動産を購入するに当たって、最初に相談した不動産会社にずっとお願いしないといけないという決まりはありません。
不動産会社と媒介契約を交わす前なら法的にも問題ないので、気になる物件の内見をした後に不動産会社を変更することもできます。
ただ、不動産会社を変更可能だからと言って、やみくもにたくさんの不動産会社に相談するのはあまり効率的とは言えません。
上述した不動産会社を選ぶ際のポイントを参考に、信頼できる不動産会社1社にお願いすることをお勧めします。
もし、不動産会社が誠実な対応をしてくれないなど何らかの理由で不動産会社を変更する場合は、購入の意思を正式に書類等で伝える前までが良いでしょう。
不動産会社を賢く選んで納得のいく不動産取引をしよう!
いかがでしたでしょうか。
この記事では、同じ物件を複数の不動産会社が取り扱うのは、
- 不動産会社が物件情報を共有している
- 売主が複数の不動産会社に売却を依頼する
という2つの理由があることと、不動産仲介業の仕組みを解説しました。
また、不動産会社を選ぶに当たって重要となる、以下の5つのポイントをご紹介しました。
- 誠実な対応をしてくれるか
- 買主側に立って考えてくれるか
- エリアや物件に詳しいか
- 不動産に関する専門的知識があるか
- 仲介手数料の額はいくらか
なお、従来は買主側が気になる物件があって不動産会社に相談する場合、その物件の広告を出している不動産会社の中から選ぶことが一般的でした。
ただ、最近ではインターネット上で自分に合う不動産会社を探し、希望の条件や気になる物件を伝えた上で仲介業務を行ってもらうケースも出てきました。
不動産会社は自分で選べる時代です。
信頼できる不動産会社を選んで納得のいく不動産取引をしましょう!
リアルは売買の仲介手数料が最大0円の不動産会社です。気になる物件や希望の条件がありましたら、ぜひお問合せください。