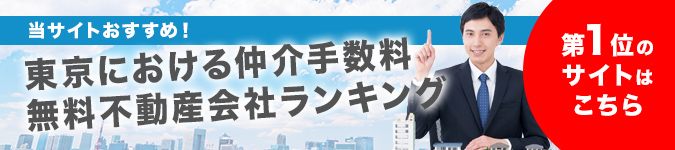不動産を購入すると、様々な税金が課せられます。
不動産購入に当たって支払う税金には、購入時や購入後に一度だけ支払う税金だけでなく、購入後毎年支払う税金もあります。
この記事では、それぞれの税金の概要と原則として決められた税額を解説。
また、税金の軽減措置や特例と、適用を受ける際の注意点もご説明します。
不動産を購入する前に、どんな税金をどれくらい支払う必要があるのか、あらかじめ把握しておきましょう。
目次
不動産購入時にかかる税金
不動産購入時に支払う税金には、「印紙税」、「登録免許税」、「消費税」、「不動産取得税」があり、いずれも1度だけ支払います。
住宅を購入した場合のそれぞれの税額は、以下のように計算されます。
| 税金の種類 | 税額計算方法(※) | 支払時期(1回のみ) |
| 印紙税 | 1万円(契約金額・借入額が1千万円超5千万円以下の場合) | 不動産売買等契約時 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額または借入額 × 0.1%~1.5% | 不動産登記時 |
| 消費税 | 建物等購入代金 × 10% | 不動産売買決済時 |
| 不動産取得税 | 土地:固定資産税評価額 × 1/2 × 3.0% 建物:固定資産税評価額 × 3.0% |
不動産購入の約6か月後 |
※軽減措置があるものは軽減措置後の税額計算方法(令和5年2月現在)
4つの税金の内、「印紙税」は契約書記載の契約金額に応じて税額が決まっており、その他の「登録免許税」、「消費税」、「不動産取得税」の税額は、「課税標準」に「税率」を乗じて算出されます。
何を基に「課税標準」が決められるかは、税金の種類によって異なります。
| 課税標準(購入代金など) × 税率 = 税額 |
なお、各税金には「課税標準」や「税額」の減額、「軽減税率」といった「軽減措置」が適用されています。
4つの税金の概要、税額や軽減措置について、以下で詳しく解説します。
印紙税
印紙税は、契約書など特定の文書に課税される国税。
郵便局や法務局などで購入できる「収入印紙」を契約書に添付する形で納税します。
不動産購入時に交わす契約書と印紙税の額
不動産購入時に印紙税の課税対象となる契約書には、不動産購入時の「不動産売買契約書」、建物新築時等の「請負工事契約書」、住宅ローン設定時の「金銭消費貸借契約書」があります。
印紙税の額は、契約書に記載されている金額に応じて下の表のとおり決められています。
| 記載された契約金額 | 税額 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
不動産購入時の印紙税軽減措置
「不動産売買契約書」と「建設工事請負契約書」については、以下のとおり、令和6年3月31日まで税額が軽減されています。
| 記載された契約金額 | 軽減後の税額 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
登録免許税
登録免許税は、不動産購入後に土地や建物等の登記を行う際に課される国税で、収入印紙で支払うのが一般的です。
不動産購入時の登記と登録免許税の額
不動産を購入すると、土地や建物を購入した際は「所有権移転登記」、建物を新築時は「所有権保存登記」、住宅ローンを利用した場合は「抵当権設定登記」が必要になります。
たとえば、住宅ローンを使って中古戸建て購入した場合は、土地の所有権移転登記、建物の所有権移転登記、抵当権設定登記が必要になります。
登録免許税は、「固定資産税評価額」(抵当権設定登記の場合は「借入額」)を「課税標準」とし、これに登記の種類に応じた「税率」を乗じて算出されます。
| 登録免許税 = 固定資産税評価額(または借入額) × 税率 = 登録免許税額 |
「固定資産税評価額」とは、土地や建物等について、固定資産評価基準に基づき評価・決定され、固定資産課税台帳に登録した価格のこと。
固定資産税評価額は、一般的に時価の7割程度と言われています。
登記の種類ごとの税率は以下のとおりです。
| 登記の種類 | 税率 |
| 土地の所有権移転登記 | 2.0% |
| 建物の所有権移転登記 | 2.0% |
| 建物の所有権保存登記 | 0.4% |
| 抵当権設定登記 | 0.4% |
不動産を購入時の登録免許税軽減措置
土地の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、令和5年3月31日まで、2.0%から1.5%に軽減されています。
また、令和6年3月31日まで、一定の要件(床面積50㎡以上など)を満たす住宅を購入した場合、建物の所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記にかかる税率が以下のように軽減されています。
| 登記の種類 | 軽減税率 |
| 土地の所有権移転登記 | 1.5% |
| 建物の所有権移転登記 | 0.3% |
| 建物の所有権保存登記 | 0.15% |
| 抵当権設定登記 | 0.1% |
新築住宅が「認定長期優良住宅」等に認定される場合は、さらなる軽減措置があります。
詳しくは後述します。
消費税
消費税は、商品やサービスの取引に際して課税される税金で、国税と地方税を合計したものです。
消費税の「課税事業者」(売上高が1,000万円を超える事業者)から物やサービスを購入する際に、消費税を支払います。
消費税は、課税事業者に納税義務がある税金ですが、商品などの価格に上乗せされて実質的に消費者が負担します。
不動産購入時に消費税を支払うタイミングは、中古建物代金、建築請負工事代金、仲介手数料、司法書士報酬、融資事務手数料などを支払う時です。
なお、土地は消費税が非課税となり、中古住宅等の売主が個人の場合は「課税事業者」に当たらず、消費税がかかりません。
不動産購入時に支払う消費税と税金の額
消費税は、購入代金を課税標準とし、税率10%を乗じて算出されます。
| 消費税額 = 代金 × 10% |
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を取得した時、家屋を新築した時に課せられる地方税で、都道府県に納税。
不動産取得税は、登記の有無や有償・無償を問わず課税されるため、不動産を贈与により無償で取得した際も、不動産取得税を支払います。
不動産取得税の額
不動産取得税は、固定資産税評価額を基にした課税標準に税率を乗じた額。
新築の家屋の場合は固定資産税評価額がまだ決まっていないため、都道府県が計算した評価額が課税標準になります。
不動産取得税の税率は原則4.0%です。
| 固定資産税評価額 × 4.0% = 不動産取得税額 |
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の軽減措置には、住宅とその敷地であれば一律で受けられる軽減措置と、住宅等が一定の要件を満たす場合に受けられる軽減措置があります。
住宅とその敷地を取得した際に一律で受けられる軽減措置
住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の土地建物の税率が3%に軽減されています。
また、令和6年3月31日まで、宅地の課税標準額が固定資産税評価額の1/2に軽減されています。
| 土地:土地の固定資産税評価額 × 1/2 × 3% |
| 住宅:建物の固定資産税評価額 × 3% |
建物が一定の要件を満たす場合に受けられる軽減措置
なお、一定の要件(※)を満たす新築住宅を取得した場合、建物の課税標準(固定資産税評価額)から1,200万円が控除されます。
また、一定の要件を満たす中古住宅を取得した場合は、建物の課税標準(固定資産税評価額)から最大1,200万円(新築時期に応じて控除額が異なる)が控除されます。
※戸建ての場合、床面積が50㎡以上240㎡以下など
| 住宅:(建物の固定資産税評価額 – 最大1,200万円)× 3% |
また、建物が上記の要件を満たす場合は土地についても軽減措置が受けられ、土地の不動産取得税額から一定額が控除されます。
控除額は、以下のいずれか大きい額です。
- 45,000円
- 土地の評価額(㎡当たり)× 1/2 × 住宅床面積の2倍 × 3%
| 土地:(土地の固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) – 控除額 |
なお、新築住宅が「認定長期優良住宅」の要件を満たす場合、さらなる軽減措置があります。
詳しくは後述します。
不動産購入後に毎年かかる税金
不動産を購入した後、不動産を保有している間に毎年かかる税金が、固定資産税と都市計画税。
これらは地方税で市区町村(東京23区内にある不動産は都)に納税します。
住宅に係る固定資産税と都市計画税は、下の表のように計算されます。
| 税金の種類 | 税額計算方法(軽減措置があるものは軽減措置後の税額) | 支払時期 |
| 固定資産税 | 土地:土地の固定資産税評価額 × 1/6 × 1.4% 建物:建物の固定資産税評価額 × 1.4% |
毎年 |
| 都市計画税 | 土地:固定資産税評価額 × 1/3 × 0.3% × 1/2 建物:建物の固定資産税評価額 × 0.3% |
毎年 |
※税率は東京23区の場合の例。固定資産税・都市計画税の税率等は、自治体によって異なることがあります。
固定資産税・都市計画税の原則的な税額の計算方法と軽減措置について、以下で詳しくご説明します。
固定資産税・都市計画税の額
固定資産税と都市計画税の額は、固定資産税評価額を課税標準とし、それぞれの税率を乗じて算出されます。
固定資産税の額
固定資産税は、土地建物の固定資産税評価額に1.4%を乗じた額です。
| 固定資産税額 = 土地・建物の固定資産税評価額 × 税率1.4% |
都市計画税の額
都市計画税は、土地建物の固定資産税評価額に0.3%を乗じた額です。
| 都市計画税額 = 土地・建物の固定資産税評価額 × 税率0.3% |
なお、固定資産税と都市計画税の納税義務者は、その年の1月1日時点の所有者。
中古不動産を購入した場合は、その年の固定資産税と都市計画税の日割り額を、売主に支払うのが慣習です。
固定資産税・都市計画税の軽減措置
固定資産税・都市計画税は地方税であるため、自治体によって軽減措置の内容が異なることがあります。
この記事では、東京23区を例に挙げて説明します。
住宅用地については、固定資産税・都市計画税の課税標準について特例措置があります。
新築住宅については、一定期間建物の固定資産税が減額されます。
| 税金の種類 | 土地 | 住宅 |
| 固定資産税 | 住宅用地は課税標準が1/6(または1/3)になる | 新築住宅は一定期間税額の1/2が減額 |
| 都市計画税 | 住宅用地は課税標準が1/3(または2/3)になる | なし |
以下で軽減措置の内容を詳しくご説明します。
固定資産税の軽減措置
「小規模住宅用地」(200㎡まで)の場合、土地の固定資産税の計算の基になる土地の課税標準が、固定資産税評価額の1/6(住宅200㎡を超える部分は1/3)になります。
| 土地の固定資産税額 = 土地の固定資産税評価額 × 1/6(1/3) × 税率1.4% |
建物については令和6年3月31日まで「新築住宅の減額」措置があり、一定の床面積要件(50㎡以上280㎡以下)を満たす新築住宅は、3年間(マンションは5年間)税額の1/2が減額されます(床面積120㎡相当分まで)。
| 新築住宅の固定資産税額 = 建物の固定資産税額 = 建物の固定資産税評価額 × 税率1.4% × 1/2 |
都市計画税の軽減措置
都市計画税についても「小規模住宅用地」(200㎡まで)の軽減措置があり、土地の課税標準は固定資産税評価額に1/3(200㎡を超える部分は2/3)を乗じた額となります。
東京23区内ではさらに、土地の都市計画税額の1/2が軽減されます。
| 土地の都市計画税額 = 土地の固定資産税評価額 × 1/3(2/3) × 税率0.3% × 1/2 |
以上のように、東京23区の「小規模住宅用地」(200㎡まで)の土地の税金は、固定資産税・都市計画税ともに課税標準が実質1/6になります。
不動産購入に関わる税金の特例
不動産購入に当たって適用可能な税金の特例には、所得税等に関する特例と、贈与税に関する特例があります。
不動産購入時における所得税の特例
不動産を購入した際、所得税等に関して受けられる特例には、「住宅ローン減税」、「認定長期優良住宅の減税」、「マイホーム買換え特例」などがあります。
住宅ローン減税
いわゆる「住宅ローン減税」とは、住宅ローンを利用して住宅を新築または取得した場合に、最大13年間一定額(年末残高 × 0.7%)を、各年の所得税から控除できる「住宅借入金等特別控除」のことで、令和7年12月31日まで適用されます。
住宅ローン減税を適用するための条件は、床面積が50㎡以上であること、年間所得が2,000万円以下であること、10年以上の住宅ローンを利用していることなど。
また、住宅ローン減税を受けるには、確定申告をすることが必要です。
認定長期優良住宅の減税
耐震性や耐久性等に優れた優良住宅の普及を促すため、「認定長期優良住宅」を新築または取得した場合は所得税をはじめ様々な特例措置が設けられています。
- 所得税の特例
- 登録免許税の特例
- 不動産取得税の特例
- 固定資産税の特例
所得税の特例
認定長期優良住宅等の場合、「住宅ローン減税」を利用する際の「借入限度額」が最大5,000万円まで拡充されます(一般住宅の「借入限度額」は3,000万円)。
また、住宅ローンを利用しない場合でも、認定長期優良住宅であればその年の所得税から一定額を控除できる「投資型減税」という特例もあります(「住宅ローン減税」と併用不可)。
正式名称は「認定住宅等新築等特別税額控除」で、令和5年12月31日まで適用可能です。
適用を受けるには、住宅床面積が50㎡以上、所得金額が3,000万円以下などの条件があり、確定申告が必要。
所得税から控除できる額は、性能強化費用相当額(一律45,300円)に床面積を乗じた金額の10%(上限650万円)となります。
| 所得税控除額 = 45,300円 × 床面積×10% |
「認定長期優良住宅」を新築・購入した場合は、上述した所得税に係る特例だけでなく、以下のように不動産取得税、登録免許税、固定資産税に係る特例もあります。
登録免許税の特例
「特定認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」を新築等した場合の建物の所有権保存登記に関して、一定の要件を満たす場合(床面積50㎡以上など)に、登録免許税の税率が軽減されます。
こちらは令和6年12月31日まで適用可能です。
| 登記の種類 | 一般住宅の税率 | 長期優良住宅の税率 |
| 建物の所有権移転登記 | 0.3% | 戸建0.2% マンション0.1% |
| 建物の所有権保存登記 | 0.15% | 0.1% |
不動産取得税の特例
新築住宅の不動産取得税について、長期優良住宅など、一定の要件を満たす場合に(床面積50㎡以上240㎡以下など)課税標準からの控除額が1,300万円に増額されます(一般住宅の控除額は1,200万円)。
| 住宅:(建物の固定資産税評価額 – 最大1,300万円)× 税率(3%) |
固定資産税の特例
税額の1/2が減額される「新築住宅の減額」の適用期間は一般住宅で3年間(マンションは5年間)ですが、認定長期優良住宅の場合は5年間(マンションは7年間)に延長されます。
減額を受けるには都税事務所への申告が必要です。
マイホーム買換え特例
「マイホーム買換え特例」は、マイホームを売却して代わりのマイホームを取得した場合に、一定の要件のもと、譲渡益に課せられる所得税を将来(買い替えたマイホームを将来売却した時)に繰り延べることができる特例。
正式名称は「特定の居住用財産の買換えの特例」で、令和5年12月31日まで適用されます。
この特例は、税金の支払い時期を繰り延べることができるものであり、税金が減税されたり非課税になったりするわけではないことに留意しましょう。
不動産購入時における贈与税の特例
令和5年12月31日まで、住宅の購入に際して、両親等の「直系尊属」から住宅取得等の資金を贈与された場合、500万円まで(省エネ等住宅の場合は1,000万円まで)の贈与に係る贈与税が、非課税になります。
贈与税が非課税になる条件として、贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること、住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下であることなどがあります。
非課税の特例を受けるには、贈与税の申告書に、戸籍謄本や売買契約書等のコピーなどの必要書類を添付して、税務署に提出することが必要です。
税金の軽減措置や特例を受けるに当たって注意すること
税金の軽減措置や特例を受けるに当たって注意すべきことを、以下でご説明します。
税金の軽減措置や特例は最新情報を確認する
税金の軽減措置や特例には、様々な適用要件が定められています。
適用条件は随時変更される可能性があり、また特例が受けられる期間も変更されることがあるため、最新情報をチェックする必要があります。
最新情報は、国税庁、総務省、国土交通省、自治体ホームページなどで確認できます。
なお、地方税の場合は自治体で特例の扱いが異なる場合があるので、購入した不動産が所在する自治体の特例を調べましょう。
税金の軽減措置や特例には様々なものがあり、適用条件も細かく複雑。不動産購入に当たっては、不動産会社や税理士などプロに相談するのも手です。
確定申告が必要なことも
税金の軽減措置や特例の多くは、自ら手続きをしないと受けられません。
今まで確定申告をしていなかった会社員の方は、確定申告が必要な特例ものもあることに注意しましょう。
不動産を購入するに当たっては、各税金の特例について、いつどんな手続きが必要になるのか確認しておくことが大切です。
まとめ
この記事では、不動産を購入するに当たって課せられる税金とその計算方法について解説しました。
不動産購入時には「印紙税」、「登録免許税」、「消費税」、「不動産取得税」を支払う必要があり、不動産購入後、不動産を保有している間は毎年「固定資産税」、「都市計画税」を支払う義務があります。
それぞれの税金には、不動産取引の活性化、良質な住宅の普及促進、税負担の公平化などの観点から様々な特例等が設けられています。
税金の特例等を受けるには、最新情報をチェックした上で、特例の適用条件、手続きが必要な場合はどんな手続きをいつまでにするのか把握しておくことが大切です。
ただ、各種税金の計算方法や特例の適用条件はやや複雑なので、不動産会社などプロに相談することもおすすめです。
不動産購入時に支払う税金以外の費用については、こちらの記事もご参照ください。