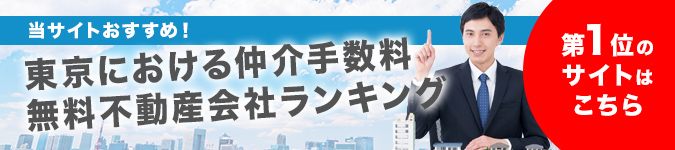住まいを検討する時、持ち家にするか賃貸にするかについて多くの方が迷われているのではないでしょうか。
月々の支払い金額で選ぶのか、それとも生涯でかかる総額で選ぶのか、考えると悩みはつきません。
この記事では、不動産を購入した場合と賃貸に居住した場合の費用の違いや、それぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。
どちらに住むのが自分にあっているのか、判断する際の参考となれば幸いです。
目次
不動産の購入と賃貸では諸費用はどう違う?
不動産を購入する場合と賃貸では支払う諸費用にどのような違いがあるのでしょうか。
それぞれの諸費用の種類と支払いを行うタイミングについて解説していきます。
諸費用の種類と支払うタイミングについて
不動産購入と賃貸では、主な諸費用の内容は以下のようになっています。
| 不動産購入 | 賃貸 | |
| 初期費用 | ・購入諸費用:新築物件価格の約3~7%、中古物件価格の約6~13% ・頭金:価格の10~20% |
・敷金:家賃1ヶ月分 ・礼金:家賃2ヶ月分 ・仲介手数料:家賃1ヶ月分 |
| 入居後 定期的に発生 |
・住宅ローン(毎月) ・固定資産税(毎年) ・都市計画税(毎年) |
・家賃(毎月) ・更新料(2年ごと) |
| 入居後不定期に発生 | ・メンテナンス費用 ・リフォーム費用 |
※住み替え時 ・引っ越し費用 ・敷金/礼金/仲介手数料 |
「初期費用」は契約時から入居前までに支払いを行います。
入居後の費用については毎月支払うものと、毎年支払うもの、2年ごとに支払うものといった形で定期的に支払いが発生するものがあります。
その他、メンテナンス費用やリフォーム費用、引っ越し費用などは必要に応じてその都度支払いを行う必要があるのです。
購入と賃貸で初期費用が大きく違う
不動産購入時の諸費用は、一般的には購入価格の約3〜7%くらいと言われていますが内訳としては以下の諸費用が含まれています。
- 印紙税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 固定資産税精算金
- 司法書士手数料
- 融資事務手数料
- ローン保証料
仮に3,000万円の不動産を購入した場合、新築の場合でおおよそですが合計で90~210万円ほど、中古であれば180~390万円ほどの諸費用がかかってきます。
これに対し、賃貸の場合は以下のような初期費用が考えられます。
- 敷金
- 礼金
- 日割り家賃
- 次月分の家賃
- 鍵交換代
- 保証料
- 火災保険料
家賃5ヶ月~8ヶ月分が目安とされますが、敷金・礼金0円の物件もあるので、物件による大きな差がでます。
仮に8万円の家賃だとすると、初期費用は40万~64万円です。
不動産を購入した場合と賃貸では数十万~数百万円の差があり、初期費用だけでもこれだけ大きな違いがあります。
購入後にも支払い続ける費用がある
不動産の購入後や賃貸の契約後、入居を始めてからも支払い続ける費用があります。
毎月支払う住宅ローンや家賃の支払いについてはほとんどの方が知っていると思いますが、その他にも支払いが必要なものがいくつかあります。
不動産を購入した場合は、固定資産税や都市計画税などの税金の支払いが毎年発生します。
固定資産税の平均額は10〜15万円ほど、都市計画税の平均額は3〜5万円です。
これらが一緒になった納付書が毎年届きます。
賃貸に入居する場合はこれらの税金を支払う必要がありません。
賃貸の場合、数年以上住み続けるとなると2年ごとに更新料として家賃の1〜2ヶ月分を支払うことが多いです。
これらは、毎月、毎年、2年ごとといったようにタイミングは異なりますが、定期的に支払うものなので、事前に資金の準備もしやすいでしょう。
この他にも支払いが発生するものとして、持ち家の場合はメンテナンス費用やリフォーム費用があげられます。
メンテナンス費用は、5年、10年、15年、20年を目安としてそれぞれ異なる箇所のメンテナンスが必要だと言われています。
しかし、全ての項目が必ず必要というわけではなく、耐久性に優れやらなくても良い場合もありますし、想定よりも早く壊れてしまう場合もあるでしょう。
リフォーム費用に関しても、いつやらなければいけないと決まりがあるわけではなく、人によって規模やタイミングは様々です。
金額も内容によって異なりますので、5万円~200万円の幅で支払う可能性があることを覚えておいた方がいいでしょう。
このように持ち家の場合は、ある程度まとまった予備資金を用意しておく必要があると言えます。
また、賃貸は生涯を通じて同じ場所に住むことは稀で、環境の変化により引っ越しをする人が多いでしょう。
その場合は、引っ越し費用や敷金、礼金、仲介手数料を新たに支払う必要が出てきます。
生涯費用でどのくらいかかる?入居から50年で比較
不動産を購入した場合と賃貸に居住した場合で、それぞれどのような諸費用が必要になってくるかイメージできたと思います。
生涯を通じての費用を計算した場合、いったいどのくらいかかるのでしょうか。
入居から50年居住した場合を想定して費用をシミュレーションしてみましたので、順番に解説していきます。
一戸建てを購入した場合の生涯費用
フラット35を提供している住宅金融支援機構の利用者調査によると、2021年度の新築取得平均価格は、建売住宅で3,605万円でした。
ちなみに同年のマンションの新築取得平均価格は、約4,500万円となりますので、下記シミュレーション金額よりも高くなります。
シミュレーションでは3,600万円の不動産を購入した場合で費用を計算してみました。
■初期費用(購入物件価格3,600万円の場合)
| 諸費用 | 物件価格の7% | 252万円 |
| 頭金 | 物件価格の20% | 720万円 |
| 計 | 972万円 |
■維持費
| 住宅ローン | 返済額 | 3,600万円-720万円 | 2,880万円 |
| 利息 | 35年払い 金利1.5%の場合 | 816万円 | |
| メンテナンス費用 | 外壁・屋根(10年ごと) | 100万円×5回 | 500万円 |
| 設備交換・リフォーム | 200万円×2回 | 400万円 | |
| 税金 | 固定資産税・都市計画税 | 12万円×50年 | 600万円 |
| 計 | 5,196万円 |
賃貸で暮らした場合の生涯費用
続いて賃貸で暮らした場合の生涯費用を見てみましょう。
家賃10万円の賃貸マンションを契約した場合で、10年に一度引っ越しをしたと仮定しました。
50年のうち5回引っ越しをすることになるので、初期費用が5回発生することになります。
また、修繕積立金や管理・共益費は、国土交通省の『平成 30 年度マンション総合調査結果からみたマンション居住と管理の現状』を用いています。
■初期費用
| 敷金(家賃1ヶ月分) | 10万円 |
| 礼金(家賃1ヶ月分) | 10万円 |
| 仲介手数料(家賃1ヶ月分) | 10万円 |
| 引っ越し費用 | 20万円 |
| 計 | 50万円 |
1回の引っ越しで50万円かかり、50年間で5かい引っ越しすると合計で250万円かかることになります。
■維持費
| 家賃(10万円/月) | 12ヶ月×50年=6,000万円 |
| 更新料(2年ごと家賃1ヶ月分) | 10万円×25回=250万円 |
| 修繕積立金(12,268円/年) | 12ヶ月×50年=736万800円 |
| 管理・共益費(1万円/月) | 12ヶ月×50年=600万円 |
| 計 | 7,586万800円 |
購入と賃貸の生涯費用の差は?
シミュレーション結果より、50年間の生涯費用を計算すると不動産を購入した場合で6,168万円、賃貸に住み続けた場合で7,836万となることが分かりました。
その差は1,668万円となり、不動産を購入する場合の方が圧倒的にお得になっています。
持ち家は初期費用が高いのが特徴ですが、住宅ローンの支払いが35年で完了する分、生涯家賃を払い続ける賃貸と金額差が広がる結果となりました。
持ち家と賃貸のメリット・デメリットについて解説
不動産を購入する場合と賃貸に居住する場合で比較するとしたら、費用面の他にはどのような判断材料があるでしょうか。
持ち家と賃貸にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
主なメリットとデメリットについて順番に解説していきます。
持ち家のメリット
家の購入は、人生において最も大きな買い物のひとつです。
マイホームを持つことを憧れに思っている人も多いでしょう。
持ち家のメリットには以下のようなものがあります。
持ち家は資産になる
購入した家は自分の資産になります。
売却すれば現金化もできますし、条件や立地が良ければ賃貸物件として収益化も期待できます。
将来子どもに相続することも考えられるでしょう。
高い資産価値があることが前提にはなりますので、購入の際は将来的な資産性も見越して検討することも必要です。
間取りや設備を自由に決められる
間取りや設備、内装や外構など自由に決められるのも持ち家のメリットと言えるでしょう。
ある程度パッケージになっているものもありますが、一から建築士と一緒に考えていくような完全注文住宅であれば細部にわたってこだわることもできます。
一生に一度の買い物なので、自由に間取りや設備を決められるというのは持ち家の大きなメリットです。
住宅ローン完済後は負担が軽くなる
不動産を購入する場合、ほとんどの人が住宅ローンを利用しています。
支払いを続けている期間は大変ですが、完済してしまえば負担が軽くなります。
多くの場合、定年前に完済してしまうので、リタイア後のお金の不安も少なくなるのではないでしょうか。
持ち家のデメリット
持ち家にはメリットもありますが、デメリットもあります。
不動産を購入する際のデメリットについて順番に解説していきます。
大きな初期費用が必要になる
不動産を購入する場合、100万円以上の大きな初期費用が必要となってきます。
賃貸の場合は、数十万円で済むので大きな差があると言えるでしょう。
内訳としては、頭金が購入価格の10〜20%ほど、購入諸費用が3〜7%になります。
頭金が少なくてすむ物件もありますが、その分住宅ローンの支払いが大きくなる傾向になります。
税金や維持費がかかる
固定資産税や都市計画税といった税金の支払いが毎年発生するのもデメリット。
賃貸の場合は必要ないので、毎年10万円以上の税金の支払いがあるのは負担に感じるかもしれません。
また、家のメンテナンスなどの維持費を、自分が負担しなければいけない点もデメリットと言えるでしょう。
住宅ローンが負担になる
希望の条件を叶えていった結果、高い金額の住宅ローンを組んで毎月の支払いに苦労してしまうことがあるかもしれません。
また、環境の変化により収入が下がってしまったり支出が増えてしまったりして、住宅ローンを支払う余裕がなくなってしまうこともあるでしょう。
この先何十年も支払いを続けなければいけないことの、精神的な負担も考えると家の購入をためらってしまう人もいるのではないでしょうか。
賃貸のメリット
世の中にはアパートやマンション、戸建てなどさまざまな形の賃貸物件があります。
賃貸にはどのようなメリットがあるのか順番に解説させていただきます。
賃貸は予算に合わせて物件を変えられる
賃貸は、物件の条件などによって支払う家賃が異なりますが、予算に合わせて物件を選ぶことが可能です。
引っ越しの手間はかかりますが、居住している途中でも家賃の安い物件に変更したり、家賃を上げるかわりに広い物件に変更したりすることもできます。
ライフステージにどのような変化があるか分かりませんので、その時の状況に応じて物件を変えられるのは精神的にもゆとりが持てるでしょう。
維持費やメンテナンスの心配がない
賃貸の経年劣化や設備の不具合については、ほとんどの場合オーナーが費用を負担することになります。
もちろん、居住者に過失がある場合はこの限りではありませんが、持ち家のように維持費の心配をする必要がありません。
さらに、設備が古くなって気になってきた場合は、新しい物件に引っ越すこともできます。
こういったことも賃貸ならではのメリットと言えるでしょう。
引っ越しが気楽にできる
費用や手間は多少かかりますが、必要であればいつでも引っ越しができる点は賃貸のメリットと言えます。
家賃の支払いを下げたい、子どもができたので広い物件に住みたい、急に転勤の辞令が出てしまったなどの環境の変化にも柔軟に対応することができます。
持ち家となると、住まいを変えるのは容易ではありません。
一度不動産を購入してしまうと、さまざまな制限が出てくるのも事実です。
生活の自由度が高いという点においても、引っ越しができる賃貸はメリットがあると言えるでしょう。
賃貸のデメリット
不動産の賃貸にはデメリットもあります。どのようなものがあるのか、順番に解説していきましょう。
自由なリフォームができない
賃貸物件はあくまで部屋を借りている状態なので、基本的にはリフォームは一切できません。
間取りを変更したり、内装を変えたり、設備を交換したりといったことが自由にできないのがデメリットです。
そのかわり、賃貸のメリットにもあるように引っ越しをすれば、理想に近い物件に変更することが可能ではあります。
家賃を払い続けても資産にならない
賃貸は住んでいるかぎり家賃を払い続ける必要がありますが、自分の資産になることはありません。
持ち家の場合は、住宅ローンを完済すれば自分の資産としてさまざまな活用をしていくことも可能です。
今住む場所を確保することはできますが、将来のことを考えると持ち家の方が魅力的に思えるかもしれません。
老後の負担が大きくなる
毎月家賃を支払い続けなくてはいけない賃貸ですが、現役で働いている間は問題ないかもしれません。
ただし、定年になり働けなくなって収入がなくなると、家賃の支払いがかなり負担に感じることでしょう。
また、退職後は収入がなくなるだけでなく、契約更新の際は保証人を付けなければいけないことも考えなくてはいけません。
さらに高齢になると身元保証人が必要になってくるケースも出てくるので、住まいを確保するのがそもそも難しい場合もあります。
購入か賃貸で迷ったときの選び方
不動産を購入した場合と賃貸に居住する場合において、費用面の違いやメリット・デメリットについて解説してきました。
それぞれ一長一短あるので、どちらを選べばよいか迷ってしまう方もいるかもしれません。
選択を迫られた際に、どのような視点で選べば良いか順番に解説していきます。
老後の暮らしやすさで考える
どこに住むかという問題は、生きているかぎりはずっと続くものです。
若いころはあまり気にしないで毎日過ごしているかもしれませんが、老後というのは誰にでも訪れます。
老後の暮らしやすさで考えると、賃貸の場合は高齢になるにつれてそもそも契約自体が難しくなってきます。
収入が少ないことや、近年問題になっている孤独死等の心配があることも理由のひとつです。
一緒に住んでくれるパートナーや、自分の子供、兄弟などがいるのであれば、賃貸の場合でもこのような心配は少ないでしょう。
駅やスーパーの近くやかかりつけの病院に通いやすい立地の物件に引っ越すことで、生活もしやすくなるかもしれません。
一方で持ち家の場合は、住宅ローンの支払いが終わっているのであれば、毎月の負担も軽くなり費用面での心配は少ないでしょう。
自宅をバリアフリーにリフォームして、ひとりでも暮らしやすくすることも可能です。
二世帯住宅として増改築して、こどもの家族と一緒に暮らすことも選択肢として考える人もいるでしょう。
老後どのような生活スタイルを送るのか、ある程度視野に入れて検討してみるのもいいでしょう。
ライフステージで考える
ライフステージによって生活環境が大きく変わる場合は、持ち家か賃貸どちらにするかの決め手となることが多いです。
具体的には、仕事の都合(転勤、転職、退職など)や家族構成の変化(結婚、出産、子供の独立など)があげられます。
ライフステージのプランが立てられていることによって、賃貸なのか持ち家なのか期間によって選択することも考えられます。
将来の資産性で考える
資産性というと、将来不動産を売却したり賃貸にしたりといったことが考えられるでしょう。
その場合は、エリアや立地などの条件であったり物件の特性であったりをよく検討する必要があります。
ここの選定を間違えると、負債となってしまうことも十分に考えられるからです。
また、自分の資産なので、将来的に子供に相続することもできます。
このように持ち家の場合は、将来の資産性を考えた場合さまざまな選択肢があると言えるでしょう。
持ち家と賃貸でそれぞれどんな人が向いている?
ここまで持ち家と賃貸についてそれぞれの視点から解説してきましたが、単純に費用面だけでは決められないことが分かったのではないでしょうか。
特徴としては、それぞれ以下のような人が向いていると言えます。
【持ち家に向いている人】
- 住宅ローンの支払いが定年までに完済できる人
- 安定した収入がある人
- 4LDK以上の大きな家が必要な人
- 転勤や転職の可能性が少ない人
- 老後に落ち着いて暮らしたい人
- 家賃を払い続けたくない人
- 持ち家を資産として考えている人
【賃貸に向いている人】
- 転勤が多い人
- 引っ越しする可能性がある人
- 相続する予定の家がある人
- 収入が不安定な人
- 住宅ローンに縛られたくない人
お金の面だけでなく、住み心地、老後、資産性、ライフステージなども考慮して自分に合う暮らし方を選ぶことが大切です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
結論としては、それぞれの人の環境に合わせて不動産の購入か賃貸を選ぶことが必要です。
ライフステージは年齢とともに大きく状況が変化していきますので、将来のことも考えてどちらがいいか検討していきましょう。